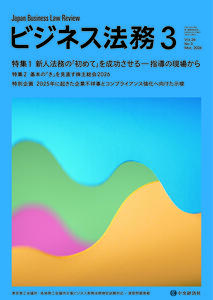
契約審査
――新人の「容量」と負荷を見極める
丸山修平
新人は,初めての契約審査において,相談者からのヒアリングやリスク評価,長文の読解や条項の理解といった高い負荷にさらされ,しばしば立ち止まる。本稿では,契約審査に必要なスキルと新人への教育の要点を挙げ,また陥りやすい失敗とその背景を明らかにし,教育者としてどこにどのように介入すべきかを具体的に示すものである。
法律相談
――解決策を示す姿勢を教える
中嶋乃扶子
会社がビジネスにおいて直面する法的課題は多岐にわたり,法務部門には日々多くの相談が寄せられる。法律相談は,その場で相談者と相対し,質疑や回答を口頭で行うという性質からか,特に新任の担当者にとっては大きなプレッシャーを感じる場面であることが多い。本稿では,法律相談対応の基本的な心構えや対応上の注意点のほか,スキルを磨くための実践的な方法について紹介する。
外部弁護士相談
――「パートナー」としての活用法を伝える
藥師神豪祐
新任の法務担当者は,外部弁護士を「答えを教えてくれる先生」と捉え,受動的な姿勢で接してしまいがちである。しかし,外部弁護士は単なる助言者にとどまらず,自社の法務機能を拡張するためのリソースとして位置づけられるべきである。本稿では,外部弁護士を「外注先」ではなく,「自社の機能を拡張するパートナー」としてマネジメントするための視点を整理する。
民事訴訟対応
――「橋渡し役」の基本を身につける
圓道至剛・堀内信宏
企業がいざ民事訴訟の当事者となった場合には,法務担当者には当該企業と代理人弁護士との「橋渡し役」が期待される。
本稿では,先輩法務部員など教育者の視点から,新任の法務担当者が初めて訴訟対応に関与する場面を想定して,その知っておくべき基礎知識や,よくある失敗とその対策等について説明する。
債権回収
――状況に応じた戦略的対応を経験させる
中森 亘
取引先の支払遅延や倒産に直面したとき,迅速かつ適切な債権回収対応が求められるが,いかにして回収の最大化を図るかは法的知識だけでなく実務的観点からの検討も求められ容易な業務ではない。本稿では「初めての債権回収」を成功させるためにフォローすべき要点を解説する。
コンプライアンス
――企業価値向上への道筋を描く
三浦悠佑
コンプライアンスは,単なる法令の遵守だけでなく,組織の将来や経営戦略の中心的な役割も担うようになった。本稿では,コンプライアンスを通じた企業価値向上への貢献に必要なマインドセットや,ヒアリング時に隠れた真実を見極めたり,組織内の協調を促したりするための共感力など,法令知識以外の重要なスキルにスポットを当てながら,コンプライアンス部門に寄せられる多様な期待や責任に応える方法について解説する。
遠藤研一郎
野球において,打率やホームランの本数は注目されても,守備のファインプレーは相対的に評価の度合いが薄い気がする。同じ選手がヒットを打って味方チームの1点に貢献するのと,良い守備をして相手に1点入るのを阻止するのでは,チームへの貢献度を考えると同じはずなのに......。なぜなのだろうか?筆者は,「貢献度を数値として表現しにくいから」ではないかと考える。
尾登亮介
ステーブルコインとは,一般的に特定の資産を裏付けとして価値の安定を図るデジタル資産を指し,裏付けのない暗号資産よりも価格が安定することから,送金・決済手段としての利用可能性が高いと考えられている。
株主総会をめぐる2025年のトレンドと2026年の展望
川井信之
2026年の定時株主総会については,株主総会に直接関係する法令や制度の改正は少なく,定時株主総会に関する準備としては,基本的に昨年と同様の準備をすれば足りる。もっとも,株主総会そのものに関する改正事項は少なくても,現在は改正に向けたいくつかの重要な動きが進行している状況であり,また,世界や日本で大きな話題になった事項は多くあるため,それらの状況を注視し,株主総会での株主からの想定質問への対応として準備しておく必要があろう。
本稿では,2025年(特に後半)における株主総会に関連する話題やトレンドを紹介し,それをふまえた2026年定時株主総会への対応・準備事項や展望を説明した後,近時の株主総会に関する考え方をふまえた,株主総会のあり方や臨み方に対する私見を述べることとしたい。
「有価証券報告書の開示時期」について
考えられる対応法
林 良樹・青木伴弥
金融庁の要請を受け,各社における有価証券報告書の総会前開示の検討は進展したが,多くは総会前日の開示にとどまり,機関投資家が望む3週間前開示を行う会社はごくわずかである。今後は,実務上の課題をふまえつつ,基準日変更等による株主総会後倒しなどの検討を行い,実効的な総会前開示を実現するための体制の構築が望まれる。
時系列でみる株主総会準備の実務
小林雄介
定時株主総会は,年に1度,経営トップをはじめ社外取締役を含む役員全員が株主と一堂に会する機会であり,会社にとっては緊張感を伴う重要なイベントである。その準備・対応期間もおおむね半年にわたる中距離走のようなプロジェクトであり,成功のためには日程表に沿った入念な準備が欠かせない。本稿では,3月決算会社(6月総会)のスケジュールを念頭に置き,1月から6月にかけてのおおむねの実務対応を時系列的に整理することで,総会準備の「基本のき」をあらためて確認したい。
株主総会招集通知・総会投影資料作成のポイント
野中翔太・谷 諭
本稿では,招集通知および総会投影資料(以下「総会ビジュアル」という)におけるデザインと見せ方が株主理解にどう寄与しうるかを,実務事例を交えて考察するものであり,前半の招集通知パートは野中が,後半の総会ビジュアルパートは谷がそれぞれ解説を担当する。なお,本文中に示す見解は,筆者らの個人的な意見であり,所属組織としての公式見解ではないことをあらかじめお断りしておく。
想定問答2026
――基本の「き」からトレンドまで
磯野真宇
2026年の定時株主総会シーズンに向けて大きな制度改正はないが,昨今の個人株主の増加をふまえた「株価」に対する経営者の姿勢を問う質問や,株価向上に向けた成長戦略を問う質問は引き続き活発になされることが想定される。本稿では,このような近時の株主からの質問の基本的なトピックスに加え,企業の動向や経済環境,国際情勢等をふまえた2026年の想定問答のトピックスについて概観する。
山口亮子・齋藤亮太・近藤知央
相場操縦が問題となる企業は多くない。しかし,本件では役員ほか社内の上位者が共犯とされているところ,共犯とされた役員の関与状況をみるに,金融機関以外の一般企業においても同様に,違法行為を承認してしまった役員が刑事事件の対象となることは十分ありうるように思われる。そこで,本稿では,本事案を他山の石として,同様の事態が生じないようにするために,企業の法務・コンプライアンス部門において何ができるかを検討したい。
今からでも間に合う
荷主における物流効率化法の対応
石山修平
物流事業においては,2023年から目まぐるしく法律が改正されている。そこで,本稿では,2023年に行われた「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」改正(「物資の流通の効率化に関する法律」へと名称も変更されている。なお,以下,2026年4月1日施行の法令を指して「物効法」といい,省令も同日施行のものを指す)のうち,2026年4月1日から施行される一定の荷主において新たに課されることとなる4つの義務について解説を行う。
なぜ「インテグリティ」なのか
中山達樹
最近,不祥事の調査報告書でも「インテグリティ」という言葉が使われるよう になってきた。なぜコンプライアンスではなくインテグリティなのか,そしてインテグリティとは何なのか。
模倣品対応の基礎
――法律上の根拠と具体的な差止方法
深井俊至
他社が自社商品の模倣品を販売している場合,自社としてどのような対応をとるべきか。他社による自社商品の模倣品販売を差し止める根拠となりうる法律上の理由と,模倣品販売を差し止めるための具体的な対応手段について,基礎的事項を説明する。
中小企業の事業承継をめぐる実務上の留意点
山下眞弘
本稿では,中小企業が円滑に事業を承継するうえで留意すべきさまざまな注意点について解説する。中小企業では日常的に総会を開催していない例があるため,いざトラブルとなると法定手続の欠如が問題とされるので,注意を要する。近年,減少傾向にある親族内承継においては,特に相続上のトラブルが絡むため,遺言など事前の相続対策が必要となる。親族外承継では,外部者への引継ぎにあたって,取引先との関係で経営理念の承継に留意すべきであり,いずれについても承継者の教育が重要となる。見落としがちなのは,労働紛争への備えである。紛争防止策として,日ごろから労使の関係を良好に保つよう心がける必要がある。
第2次トランプ政権の通商政策
――2025年の振り返り
宮岡邦生
本稿では,2025年における第2次トランプ政権の通商政策を,関税,対中政策,外交・安全保障の観点から振り返り,日本企業への影響と2026年に向けた見通しを述べる。
森・濱田松本法律事務所外国法共同事業編
2025年11月、12月の法務ニュースを掲載。
■ICMA,「気候移行債ガイドライン」の策定等を公表
■ISSB,自然関連の開示にTNFDの枠組みを採用する方針を表明
■公取委等,「経済安全保障と独占禁止法に関する事例集」を公表
■法務省,「民法(遺言関係)等の改正に関する中間試案」に関する意見募集の結果を公表
■法務省,「民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案」に関する意見募集の結果を公表
■労働政策審議会,「同一労働同一賃金ガイドライン見直し(案)」を公表
■改正マンション関係法の施行に伴う関係政令を閣議決定
■環境省,国連気候変動枠組条約第30回締約国会議,京都議定書第20回締約国会合およびパリ協定第7回締約国会合の結果について公表
■ISS,2026年版議決権行使助言方針を公表
■消費者庁,「現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会」を開催
■金融庁,「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)を公表
■政府,「金融の円滑化に向けた取組及び事業者支援の徹底について」を要請
■国税庁,令和6事務年度法人税等の調査事績の概要を公表
■内閣府,「人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性確保に関する指針(案)」に関する意見募集を実施
■スマホソフトウェア競争促進法施行
企業法務担当者のための「法的思考」入門
最終回 企業形態と資本集中の論理
野村修也
企業を契約の束と捉えるとすると,そこには契約自由の原則が妥当するはずである。しかしながら,会社の場合には,契約交渉のテーブルに着けないステークホルダーがいること,規模が大きくなればなるほど交渉のための取引費用がかさむこと,意思決定方法や責任の仕組みが千差万別であれば,かかる組織と取引する相手方にも多額の取引費用が生ずること等の理由から,会社法は,所有の論理も加味しながら,合理的な利益調整の仕方を「標準書式」として定型化し,その大部分を強行法規として提示する手法を用いている。
株主総会のDX化――壁を乗り越えるために
最終回 株主総会の在り方に関する規律の見直し
――株主との建設的な対話に向けて
牧村卓哉
現在,法制審議会会社法制(株式・株主総会等関係)部会(以下「部会」という)においては,「株主総会の在り方に関する規律の見直し」が議論されている。従来の「会議体」として開催することを前提とする株主総会のあり方は,大きな転換期を迎えている。
最新判例アンテナ第92回
外貨建取引によって実現した為替差益による所得の把握において基準とすべき通貨は邦貨であると判断された事例(東京地判7.2.5LEX/DB 25616570)
三笘 裕・平松慶悟
Xは,2017年から2018年に,A銀行から4回に分けてドル建てで借入れ(以下「本件借入れ」という)を行って外貨預金とし,当該外貨預金を用いて4件の米国不動産を取得(以下「本件不動産取引」という)した。
差止請求事例から考える 利用規約のチェックポイント
最終回 転売を禁止する条項等
小林直弥・土田悠太
消費者契約においては,消費者の転売を禁止する条項や,危険負担を消費者に負わせる条項が定められることがある。連載最終回では,近時の差止請求事例等を紹介しながら,これらの条項に関する規約作成上の留意点について解説する。
当局のプラクティスから学ぶ米国法
最終回 米国制裁と輸出管理
――日本企業が今から備えるべき戦略的視点
ナビール・ユセフ ステファニー・ブラウン・クリプス・山田香織
地政学リスクの高まりを背景に,米国によるロシア・中国への制裁は,日本企業にとって単なる規制リスクにとどまらず,重要な戦略的示唆を含んでいる。これらの制裁・輸出管理措置に違反しない体制の構築は,企業価値の維持に直結する要素である。特に高リスク地域との取引において,適切な未然防止策を講じることは,企業の信頼性を高め,長期的な競争力を確保する鍵となる。本稿では,日本企業が備えるべき戦略的視点を解説する。
分野別 規制改革制度のトレンドと活用法
最終回 観光・まちづくり
荏畑龍太郎・池知貴大
最終回では,まずわが国の観光・まちづくり分野に関する政策の動向を紹介し,当該分野における規制改革制度のトレンドを分析する。観光・まちづくり分野は,異なる利害を調整することが実務上の核心となる領域であるが,こうした複雑性を抱える観光・まちづくり分野に携わる読者の一助となれば幸いである。
法律事務所をフル活用しよう!専門弁護士に聞くAI時代の新常識
最終回 法務部と法律事務所とAI
――新時代の協働関係づくりに向けて
金子晋輔
全6回連載の総括回。本連載を通じてみえた法務部と法律事務所とAIとの新たな協働のあり方について,尾下大介弁護士(CrossOver法律事務所 代表弁護士)と片岡玄一氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)との鼎談を実施する。加えて,今後の効果的な協働に向けて,法務部と法律事務所のためのチェックリストを提供する。本連載の振り返り,読者コメントの紹介,今後の展望についても言及する。
事例でわかる「AI活用」ことはじめ
第3回 法令・判例等リサーチ
坂 昌樹・山田健介
企業法務における法令・判例リサーチは,日々の業務の中核を占める重要な活動である。しかし,法令の改正頻度の増加,判例の蓄積,国際取引の増加による各国法制の調査必要性など,リサーチ業務は年々複雑化している。本稿では,AI技術を活用した法令・判例リサーチの効率化と高度化のポイントについて解説する。
商業登記実務基本マスター
第3回 商業登記の関連情報
鈴木龍介・真下幸宏・山本結香
商業登記に関する情報の確認は,企業の法務担当者が習得しておくべき基本的な業務の1つである。たとえば,取引先等の調査を行う場合,当該情報を適切に取得し,正確に把握することが必要となる。
連載第3回では,商業登記に関連する情報の概要,取得方法のほか電子認証制度について取り上げることとする。
法と人類学―法がつくられるとき―
第8回 「長期的な平穏」を追求する法文化
原口侑子
第6,7回と藪本さんがラオスやカンボジアの実務のなかで指摘されていた「ルールを守る」と「関係を壊さない」の「間」。アフリカ各地の法制度も(建前としての成文法はともかく)その「間」で運用されていると感じます。
法務担当者のための独占禁止法"有事対応"ガイド
第5回 優越的地位の濫用事件と確約手続対応
神村泰輝
本連載第5回は,優越的地位の濫用事件の行政調査および確約手続への対応を取り扱う。近時の法改正で導入された確約手続は,違反被疑事件の早期解決に向けた重要な選択肢である。本稿では,規制の基礎を確認したうえで,確約手続利用の留意点を解説する。
企業法務のための外為法入門
第4回 投資管理
大川信太郎
本連載の第4回では,法第5章(対内直接投資等)に関する規制のうち,対内直接投資等および特定取得に関する事前届出制・事後報告制を解説する。