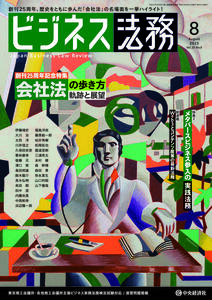
株主総会の法制と実務の変遷
松井秀樹
本稿は,平成と令和の約30年間超にわたる株主総会に関する主要な法令改正や実務の軌跡を概観するとともに,株主総会についての今後の展望について所感を述べるものである。
勧告的決議
福島洋尚
会社法の制定前後に現れ,その後広く普及したものとして,いわゆる勧告的決議がある。会社法制定前にはほぼ議論がなかったにもかかわらず,会社法の制定前後に株主の意思確認手段として理解されるようになったが,近時,勧告的決議の意義そのものについて変容ともいえる状況が生じている。
少数株主による株主総会招集請求・業務財産調査者選任請求
太田 洋
近時,少数株主による株主総会の招集請求や業務財産調査者の選任請求が,少数株主によるガバナンス是正といった従来の想定とは異なる形で用いられている。これらの問題に対処するため,近時の用いられ方を前提とした新たな制度のあり方が議論されるべきである。
株主平等の原則
山下徹哉
平成17年制定の会社法は株主平等の原則の一般原則について明文規定を置き,また,裁判実務でも,法制度の濫用的利用に対する対抗法理として用いられることが増えている。本稿では,以上のような変化の理論的含意について解説する。
定款自治
大川 治
平成17年会社法の立法においては,「当事者の選択肢の拡大」が最も基本的な視点とされ,「会社の機関の設置等における定款自治の範囲の拡大」が企図されるなど「定款自治」が大きくクローズアップされた。本稿では,定款自治をめぐる経緯や論点を振り返りつつ,定款自治の現状とこれからを展望してみたい。
商業登記
鈴木龍介
わが国の商業登記制度は,いわゆる旧商法(明治23年法律32号)が明治26年に施行されたことにより始まったわけであるが,時代の要請等を背景にさまざまな変遷をたどり,現在に至っている。本稿では,商業登記,とりわけ会社登記について,その歩みを概観しつつ,今後重要になるであろう視点をふまえ,これからのあり方に若干の考察をくわえることとする。
株主代表訴訟
本村 健
株主代表訴訟制度は,時代背景を背にしつつ,法改正とインパクトある判例群に彩られている。判例を通じた法規範形成は,役員責任制度の進化を促し,取締役会の行為規範も示す。訴訟事件と改正事項を交え振り返り,高度化・精緻化が進む状況を念頭に展望を考える。
役員責任追及訴訟以外の会社訴訟
圓道至剛
広義の会社訴訟のうち,取締役会議事録の閲覧謄写許可請求事件と,経営統合差止めの仮処分命令申立事件を取り上げる。前者については,多くの学説に反して,裁判所による慎重な審理判断を希望する私見を示す。後者に関しては,会社訴訟にも日本版アミカス・キュリエを導入することを提言する。
取締役の義務と責任
伊藤靖史
わが国の取締役の義務と責任に関する議論は,ここ25年の間に大幅に進展した。裁判例の蓄積によって,取締役の善管注意義務の内容は相当程度明確化しており,これは判例による法形成とも評価できる。もちろん,なお明らかでない点もあり,一人会社や,利益相反の要素を含む行為に関する取締役の義務内容は,その例といえる。
役員報酬・ストックオプション
高田 剛
業績連動報酬や株式報酬に関する一通りの法的規制が整備された今,企業価値を創造する仕組みとして経営者報酬の設計効率を高め,透明度の高い運用をすることが求められる。
社外取締役の今昔
中西和幸
社外取締役の歴史は意外と新しい。そして,社外取締役に期待されている職務や機能は,時代とともに変化している。このような社外取締役の歴史のなかでは,裁判や機関投資家の考え方,また日本の証券市場における株価低迷など,さまざまな要素が絡み合っている。しかし,会社法を担う者の世代交代により,こうした歴史が忘れられてしまう可能性もある。そこで,短いながらも社外取締役の歴史を振り返ってみたい。
社外取締役の役割・実効性
島田邦雄
理念と現実が乖離することは珍しくないが,社外取締役に関しては,その問題が常に議論を呼ぶところである。期待される役割をふまえつつ,現実に生じている事象の紹介を通じて,社外取締役のあるべき姿とその実効性を検証する。
会社法学にとっての経済学の必要性
田中 亘
会社法学にとって,経済学の知見は,有用というよりは必要不可欠である。本稿では,株主第一主義の是非という論点を例に挙げて,そのことを示してみたい。
機関設計
川井信之
本稿では,会社法における機関設計のうち,上場会社における機関設計について,具体的には,上場会社が現在選択可能な3類型(監査役会設置会社,監査等委員会設置会社,指名委員会等設置会社)について,それぞれの歴史を振り返りつつ,それらの現在の状況と将来の展開等について述べることとする。
M&A・買収防衛策,株主提案のパラダイム変化
森 幹晴
変わりゆくM&A・買収防衛策,株主提案の実務。株式持ち合いの解消,ガバナンス改革,社外役員の責任強化,アクティビストの存在感の高まり。パラダイム変化に乗り遅れるな。
公開買付け
松尾拓也
2006年以降大きな改正が行われていない公開買付規制であるが,2023年3月2日,金融審議会総会が開かれ,公開買付規制の適用範囲(市場内取引の取扱い,閾値等)の見直しを含む具体的な課題が掲げられた。改正が実現した場合には,わが国の上場会社のM&A実務に重要な影響を及ぼす可能性があり,注目に値する。
組織再編の差止請求と子会社株主による親会社等の責任追及
後藤 元
平成26年改正会社法では,組織再編等の差止請求権の対象が拡大された一方で,子会社少数株主による親会社等の子会社に対する責任追及の導入は見送られた。本稿では,これらの制度に関する同改正後の動向をふまえて,今後の課題を明らかにする。
スクイーズアウト取引における「公正な価格」
藤原総一郎
株式買取請求権を行使した場合の買取価格が,「ナカリセバ価格」から「公正な価格」に変わったため,今後は,合併等の組織再編に伴ってシナジーが生ずる場合であれば,そのシナジーも織り込んだ価格で買い取られることになる。
比較法の方法論
森田 果
本稿では,比較法の一般論,および,会社法とファイナンスにおける比較法の展開,の2点について簡単に検討したい。
モデルとしての英国会社法の展開
内藤央真
英国会社法の歴史的展開と現行法を振り返り,改正案や技術革新による課題を紹介する。信頼できる枠組みとして機能するために,英国会社法にはいま,変革が必要である。
新株予約権・社債
栗林康幸
新株予約権が実務においてストックオプション,資金調達,買収防衛策,M&Aの手法などさまざまな方法で利用され,それに対して会社法がどのように対応してきたか,また,社債について,社債管理者があまり利用されなかった状況に対応して社債管理補助者制度が導入された背景について,それぞれ概観するとともに今後を展望する。
IFRS適用と分配可能額規制
髙木弘明
会社法会計が企業会計を前提としているなかで,将来的に個別計算書類へのIFRS適用が再検討される場合,分配可能額規制・資本制度について改めて検討を迫られる可能性がある。
分配規制のパラダイム転換
弥永真生
連単分離を図るか,そうでなければ支払不能テストによる分配規制を導入することによって,有用な連結会計情報を提供できるようにすることが検討されてもよいのではないか。
内部統制システム
三浦亮太
内部統制システムに関する会社法の規律は平成26年改正以降変更されていない。取締役会において決議すべき事項が法務省令で規定されている理由は機動的な改正のためであり,時機に応じた改正やプリンシプル・ベースへの変更等も検討に値する。
ガバナンスと企業不正
山口利昭
企業不正への対応として会社法で語られてきたガバナンスについては,主に不正予防的見地による議論が多かった。しかし企業統治改革の流れにおいて,経営者の法的責任よりも経営責任に光があたることが増え,むしろ危機対応に関する議論が主流となりつつある。今後は危機対応を想定したガバナンスを検討する必要がある。
ソフトロー活用の進展
浜辺陽一郎
会社法分野でもハードローの限界を克服するため,ソフトローの活用が模索されてきており,企業社会はその対応に迫られている。今や企業法務においてソフトローも無視できない重要領域である。ソフトローの弱点をふまえながらも,前向きに取り込むことが持続的成長を目指す企業にとっては賢明な選択となろう。
サステナビリティとコーポレート・ガバナンス
久保田安彦
本稿では,サステナビリティ論を取り上げ,その背景事情や近時の動向を概観したうえで,株主主権の評価やコーポレート・ガバナンス上の課題に言及する。
コーポレート・ガバナンスと執行役員制度
澤口 実
本誌創刊とほぼ時を同じくして誕生した執行役員制度は,今日に続くガバナンス改革の端緒であった。法令に根拠のない動きであることや,グローバルスタンダードを意識した点においても,近時のコーポレート・ガバナンスの潮流を象徴する動きであったといえる。
中村直人
会社は,企業価値を向上させて,株主に利益を配分するためにある。経営の最終決定権は株主に帰属する。バブル崩壊後の経済危機の中で規制緩和の商法の改正が続き,最終的に平成17年に会社法が制定された。株主主権といわれる考え方をとり,企業の世界的な競争力の向上を目指した。会社法は完成品として登場した法律である。その後平成26年と令和元年に改正がなされたが,根本的な改正ではない。現在,経済界からも学会からも重要な改正要望は示されていない。
池本和隆
令和8年度末を目途に,紙の約束手形の利用廃止が目指されている(小切手も同様)。もっとも,企業における準備は,順調とまではいえないようである。本稿では,一金融機関の立場から,手形・小切手を利用する企業の担当者に対し,電子的手段への移行(以下「電子化」という)に向け準備し得ることにつき,特に手形に絞って一考を加えたい。
デジタルツインにおける他社知的財産権の侵害防止
藤枝典明
メタバース等をめぐる法的課題等の議論が活発となっている現状をふまえて,メタバース事業に参入する事業者が,他者の知的財産権を侵害しないために理解すべき制度(特にデザイン保護に関する法制度)と対応策を,現実世界の再現(デジタルツイン)に関する事例をふまえて検討する。
二次創作市場のマネタイズとメタバース
高瀬亜富
本稿は,IPホルダーによるメタバースを利用した二次創作市場のマネタイズを想定し,これに関連する法的論点を検討するものである。検討にあたっては,「ビジネスモデルX」という架空のビジネスモデルを措定した。従前からファンによる二次創作を許容するための「二次創作ガイドライン」を策定するような試みはみられたが,こういった試みと「ビジネスモデルX」の異同をふまえた検討が有益と思料する。
メタバースビジネスにおける契約実務
根岸秀羽
現在のところメタバースに特化した「メタバース法」のような法令が存在しないなか,メタバース上の法律問題を検討するうえでは,当事者間の契約が特に重要な意味を持つことになる。本稿では,各プレイヤーの視点からメタバースビジネスにおける契約実務を検討する。
他社メタバース利用時の不正侵入リスクと各種法規制
稲垣紀穂
本稿は,事業者が他社の提供するメタバースをビジネス利用する場面に焦点を当て,当該利用方法につき①他者のメタバースを社内業務用のツールとして利用するもの,②他社のメタバースを商品・役務等を提供するための場として利用するものに整理し,それぞれの具体例を紹介したうえで,①については不正侵入リスク,②については各種法規制等の留意点の検討を行うものである。
メタバースの周辺問題――NFT・DAOに焦点をあてて
多良翔理
ここまでは,メタバースに直結する問題について取り上げてきたが,本稿ではNFTやDAOといった近年話題となっているメタバースの周辺問題を取り上げ,法的整理や,利用の際の注意点,今後の課題などを検討したい。
福原あゆみ
経済産業省は,2023年4月,企業が人権デュー・ディリジェンス等の取組みを進める際の実務的な参考資料として,「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」の実務参照資料を公表した。同資料は,企業における取組みの出発点となる人権方針の策定および人権デュー・ディリジェンスのうちのリスク評価に関する点を中心に具体的手法を示したものであり,企業の取組みにおいても有用と思われることから,その概要を解説する。
再考:取締役会評価
――取締役会の役割から評価実務を考える
池永朝昭
上場企業で取締役会評価は広がりをみせており,取締役会の機能が強化されるのに役立つという評価もみられるが,業績改善や企業価値の中期的向上につながっているという報告がない。はたして取締役会評価はそれでよいのか。本稿はこの疑問から出発する。
越境リモートワーク実施上の法的留意点
西原和彦・阪口英子
新型コロナウイルス感染症の流行を機に日本でも広くリモートワークが普及し,今や国境を越えたリモートワークを実現している企業も多くある。リモートワークは情報通信技術の発達によって可能となった新しい働き方で,国内でも従来と異なる対応が求められるところ,国境を越えるリモートワークには外国法も適用されるためさらに法律関係も複雑になる。本稿では,企業と従業員が直接労働契約を締結するケースを対象として検討する。
稲垣弘則・田村海人
近時,Web3の動きが世界中に広がっており,日本においても法政策が進んでいるが,特に日本の強みとなり得るコンテンツ産業におけるWeb3の活用可能性が期待されると同時に,さまざまな課題が浮き彫りとなっている。そこで,本連載では,コンテンツ産業におけるWeb3の活用可能性と実務上の課題について概説する。
最新判例アンテナ
第61回 利益相反取引に該当する他社株式の取得取引において,取得株式の客観的評価額と実際の取得価額との間に乖離があったとしても直ちに会社に損害が発生したとはいえないと判断した事例
三笘 裕・布山雄大
A社は,東証2部(当時)上場の株式会社であり,Y1,Y2およびY3(以下「Yら」という)はA社の取締役であった。Y1は自身が代表を務めるB社の株式を100%保有し,B社傘下のC社およびD社(以下「C社等」という)の代表取締役の地位にあった。
LEGAL HEADLINES
森・濱田松本法律事務所 編
ビジネスパーソンのためのSDGs相談室
最終回 2030年にかけてのSDGs
山本哲史
Q:これまでの連載を通じて,SDGs/サステナビリティについての理解が進みました。SDGsは2016年から30年までの国際目標と聞いています。ちょうど折り返し地点ですが,本連載の最後に,今後の展望やビジネスパーソンとして押さえておくべきポイントを教えてください。
ITサービスにおける「利用規約」作成のポイント
最終回 プラットフォームビジネスにおける利用規約
中山 茂・古西桜子・柿山佑人
最終回である今回は,いわゆるプラットフォームに関連するビジネスにおける利用規約に関して,前提となる法律関係の整理や検討すべきポイント,関連法令などを解説する。近年発達・拡大をみせるプラットフォームビジネスにおいては,消費者取引の「場」を提供するサービスという法的地位の特殊性もあり,また,取引DPF法をはじめ,法規制の整備も進められているため,今後も法規制の動向をふまえながら対応していく必要がある。
考える法務――基本と初心とささやかな試み
第2回 次は勝つ
大島忠尚
裁判所ウェブサイトには,「我が国は,正しい裁判を実現するために三審制度,すなわち,第一審,第二審,第三審の三つの審級の裁判所を設けて,当事者が望めば,原則的に3回までの反復審理を受けられるという制度を採用しています。第一審の裁判所の判決に不服のある当事者は,第二審の裁判所に不服申立て(控訴)をすることができ,第二審の裁判所の判決にも不服のある当事者は,更に第三審の裁判所に不服申立て(上告)をすることができます」とあります。裁判に関する基本中の基本です。今回はこの三審制について,実際のデータを確認しつつ,考えてみたいと思います。
怒れる弁護士「アンガーマネジメント」を学ぶ。
第4回 自分の価値観と上手に付き合う方法
宮山春城
「機嫌」という言葉の語源をご存じでしょうか。もともとは,人に嫌われたり人を不愉快にするような行為は慎むように,という仏法の戒めだそうです。とあるアンケートによると,「仕事ができる人」と「機嫌がいい人」では,後者のほうが一緒に仕事をするうえで好ましいと思われやすいとの結果が出ています。
双日法務部のリーガルオペレーション
第5回 グローバル法務
澤井信宏
総合商社は海外での事業展開とセットで歴史を重ねており,その時点における事業環境に応じる形で進出と撤退を繰り返しつつも,一貫して世界各地に支店,現地法人あるいは駐在員事務所等の拠点を置き,現地の従業員とともに業務を展開してきた。現在の双日においても世界各地に拠点を置き,日本の本社の経営方針をふまえつつ現地の法令やルールに則った運営を行っている。本稿では,双日の海外における法務体制をご紹介しつつ,海外の法務組織との連携においてこれまで行った試行錯誤と課題について振り返ってみたい。
弁護士のとあるワンシーン with 4コマ
Scene5 弁護士の時間捻出法
中村 真
多くの法律家がそうであるように,私も限られた時間で最大限の効果が得られるように,日々悪戦苦闘しています。気を失いそうな過密スケジュールの中で,時間を効率的・効果的に管理する方法は,弁護士としてのキャリアの成功と個人的な充実感,家族の安寧のためには欠かせません。
ケースで学ぶ ビジネスと人権
第5回 人権DD④――取組みの実効性評価と説明・情報開示
坂尾佑平・岩崎啓太
連載第2回より,「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(以下「本ガイドライン」という)における人権尊重の取組みの各論として,人権デュー・ディリジェンス(以下「人権DD」という)に関するケーススタディを行っており,連載第2回では人権DDの4つのプロセスの1つめにあたる「負の影響の特定・評価」,連載第3回および第4回では2つめのプロセスである「負の影響の防止・軽減」について,それぞれのポイントを解説した。今回は,人権DDに関する解説の締めくくりとして,人権DDの3つめのプロセスである「取組みの実効性の評価」および4つめのプロセスである「説明・情報開示」について,本ガイドラインをふまえたポイント等を説明する。
ストーリーでわかる 労働審判の基本
第3回 答弁書の作成等①
福谷賢典・山下 諒
【前回までのあらすじ】乙社の福岡事業所に3年間勤務し(1年の有期労働契約を2回更新),2022年12月末をもって雇止めとなった甲が,雇止めの無効を主張し,乙社を相手方として福岡地方裁判所に労働審判の申立てを行った。乙社の東京本社の人事部担当者は,顧問のY弁護士に相談し,乙社の代理人に就いてもらうことにした。Y弁護士は,福岡事業所の関係者から詳しく話を聞きたいと希望した。
IPO準備における会社法の基礎
第3回 取締役会の適切な運営⑴
青野雅朗
本連載は,上場準備において比較的論点になりやすいトピックという切り口から,全6回の予定で,会社法の基礎を振り返るものである。第3回は,取締役会の運営に関する論点について取り上げる。取締役会は株式会社の要となる機関であり,その運営に関する論点も多岐にわたることから,複数回に分けて取り扱う。
マンガで学ぼう!! 法務のきほん
第18話 転職者による情報流出
淵邊善彦・木村容子
転職者が,転職先に秘密情報を持ち出して,秘密保持義務違反や不正競争防止法違反が問題になるケースが増えています。秘密情報は,不正競争防止法上の一定の要件を満たせば「営業秘密」として保護され,差止請求や損害賠償請求等が可能です。
アメリカ民事訴訟実務の基礎と留意点
第2回 訴訟はどのように開始されるか
奈良房永・笠継正勲
米国連邦裁判所で正式に訴訟が開始されるためには一定の手続が必要であり,訴状が裁判所に提出されると最初の攻撃・防御の段階となる。原告側の手続に不備があれば被告側はまずそれを争うことになる。被告側は最初の選択肢を理解し,初期段階で応訴方針を定める必要がある。訴訟開始段階での争い方は,当事者間の和解に向けた交渉力や駆け引き,裁判官の心象にも影響するため,送達を含めた手続を正確に理解しておくことが重要である。
米国法上の不動産所有権および賃借権の基礎――日本法との比較
第3回 米国不動産の賃借権
ティモシー・ハマースミス・加藤奈緒・白井潤一・髙橋梨紗
本連載では,米国における不動産の所有権・賃借権に関する概念・制度等について日本法と比較しながら解説している。第3回では,米国不動産の賃借権について取り上げる。